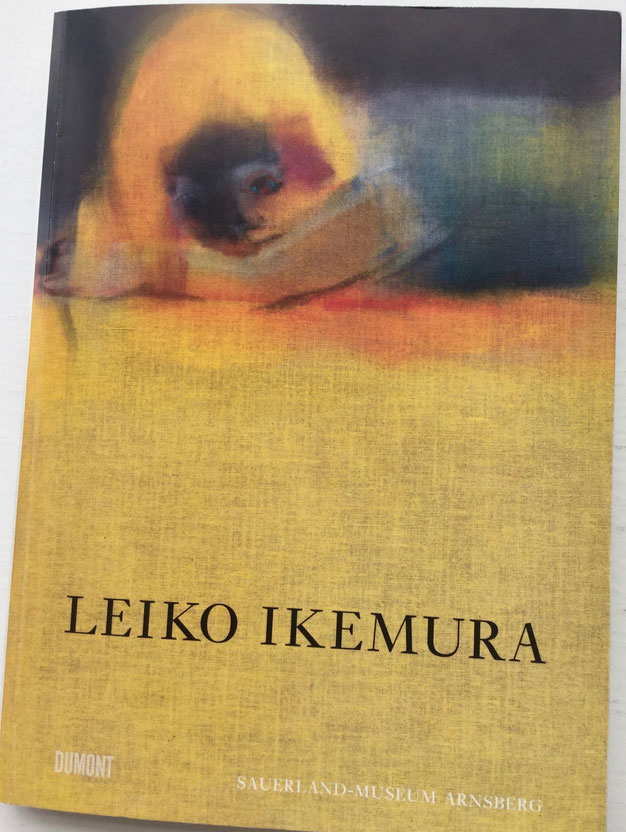
次の日は、午前中に乃木坂の国立新美術館で開催していた「イケムラレイコ 土と星」展を観に行きました。
国立新美術館は、東京ミッドタウンに2007年に開館した、黒川紀章設計の波打つようなガラスのカーテンウォールの形状が特徴的な建物で、内部には大きな展覧会場がいくつもある「ミュージアムコンプレックス」です。
イケムラレイコというヨーロッパ在住の作家のことは以前から美術雑誌などで知っていましたが、実作を見るのは今回が初めてです。
イケムラ氏は70年代に渡欧して、まずは集中的にドローイングを描くことからキャリアをスタートさせ、現在では絵画と陶芸による作品制作のほか、ドイツの美術大学でも教鞭をとっておられるとのこと。
展覧会では、そのような活動の中から選ばれた沢山の作品が展示されていましたが、全体的な印象として、初期のドローイングの線の持っている無垢な感覚が、通底するようにそのまま絵画や陶芸作品でも現れているように思いました。ヨーロッパという絵画や芸術の歴史の厚みのある地において、作家として自分の最良の部分を打ち出して表現を確立しようとするとき、この無垢な部分を守りつついかに表現を展開していくかということは、大きな課題であったものと推測されます。
展覧会の最後の部屋では、最近作の大画面の絵画が広い空間にゆったりと展示されていましたが、そのような大画面の作品でも、水彩画のような簡潔な線と「間」を生かした画面構成によって、東洋の山水表現のような風情を生んでいました。


午後からは埼玉の川口市に移動し、川口市立アートギャラリー・アトリアで開催中(〜5/12まで)の「絵画展・・・なのか?」展を観に行きました。この展覧会は、オリジナルな立場で「絵画」作品を制作している関西出身の3名の美術作家が参加する企画展です。この日は展覧会初日で、出品作家によるギャラリートークもあり賑わっていました。
出品作家の1人である原田要さんは30年以上前からの知人で、その頃から個展などの度に作品を拝見していますが、発表の初期段階から一貫して、木で造形物を作りその表面にペイントしたものを「絵画」として発表されています。キノコ状のもの、壺状のもの、お皿のようなものなど形態は様々ですが、木で作った立体の表面に鑿でさらに彫り込み、そこに顔料でペイントしていくという手法は共通しています。それは、絵画を描くという自明の方法を一旦解体し、視線を集める装置としての機能や、支持体と表面の関係などを検討し直し、原田さん独自の考えで再構築されたものとしての「絵画」です。
今回の展覧会では、これまでに発表した大作を広いギャラリーの空間や壁面に多数配置し、見応えのある展示になっていました。
(下の展示風景の写真は、原田要さんのフェイスブックページから許可を得て転載しました。)


今回の東京現代絵画ツアーの最後は、六本木の森美術館で開催中(〜5/26まで)の「六本木クロッシング2019 : つないでみる」展です。「六本木クロッシング」展は、3年に一度開かれる日本の若手作家の動向を概観する現代美術展で、今回は25組の作家による様々な表現形態の作品を展示しています。

森美術館は六本木ヒルズにそびえ立つ森タワーの53階にありますが、エレベーターで上がって美術館に行くまでに、東京をぐるりと見渡せる展望スペースを必ず通ります。
写真の下の方にはすぐ近くの東京ミッドタウンにある国立新美術館、その向こう(写真の真ん中あたり)には建設中の神宮外苑の新国立競技場、さらにその向こうには新宿の高層ビル群が見えます。

「六本木クロッシング」展でも、彫刻や立体造形、インスタレーション、映像、写真などの作品が展示されている中、数少ない絵画作品にやはり注目してしまいます。榎本耕一(写真上)によるバンド・デシネ的なイメージによる精密な絵画も楽しめましたが、とりわけ杉戸洋の、木枠に木片やキャンヴァス布などをピンやタッカーで留めたり、パネル同士にスポンジを噛ませて重ねたものを台に載せ、壁に立て掛けて展示している「絵画」の連作を注目して観ました。
杉戸氏の同様のアプローチによる作品は、以前にも東京都美術館や小山登美夫ギャラリーでの個展の際に観たことがありました。その時はあまり「引き」のない空間構成にしてあったためか、素材のチョイスやそれらのブリコラージュ的な扱い方の手なみに感覚の面白さを感じたものの、作品としてはやや弱い印象だった記憶があります。しかし今回は広い空間の中に展示されているので作品全体の様子がはっきりと見えてきます。

僅かにペイントされたりラメをまぶされたキャンヴァス布が、重ねられて木枠にピン留されることによって生じる表情や、木枠と布や布同士に生じる細かい空間などを丹念に観たり、作品から離れて、そのように組み合わされ並べられた全体像が空間の中でゆったり存在している様子など、行ったり来たりしながら楽しんで見ることができました。
作品の見かけなどはシュポール/シュルファスを彷彿とさせるのですが、同時に、作品を見ていて私の頭に浮かんだ言葉は「アンビエント」でした。ある特定のイメージがキャンヴァス内から主張してくるような絵画ではなく、かつてブライアン・イーノが提唱した環境としての音楽のように、日常に普通にありそうな素材がゆるやかに組み合わさって、空間の中に半分溶け込むように存在する、そんな絵画のあり方です。(そういう意味では、東京都美術館や小山登美夫ギャラリーで見た作品の方がアンビエント的だったのですが。)ただ、そこで日常性の中に埋没してしまわないで、それが確かに絵画(あるいは「作品」)であるということはどういうことなのか?そしてそうあらしめるものは何か?という問いが残ります。そういう意味では、この作品は見かけのさり気なさに反して、その実、絵画(あるいは「作品」)の成立の根拠を問うという非常にラディカルな問題を内包しているようにも思えました。(Y.O.)



